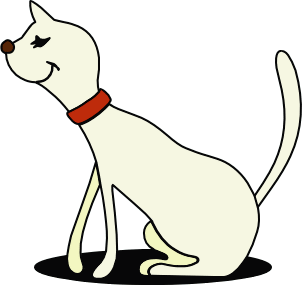| 相続発生後の各種手続きをご紹介いたします。 | ||||||||||||
| 預貯金の名義変更! | ||||||||||||
| 一部の相続人が預貯金を勝手に引き出すことを防止するため、金融機関は預金者(被相続人) の死亡を確認すると同時に被相続人名義の口座を凍結します。預貯金の凍結を解除するには 必要書類を提出しなければなりませんが、各金融機関により必要な書類や手続きが変わりま すので、一度金融機関へ問い合わせてみてるのがもっと確実になります。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 金融機関指定の預貯金払戻請求書、名義書換請求書 被相続人の預貯金通帳・届出印・キャッシュカード 被相続人の戸籍・除籍謄本・改正原戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書 遺産分割協議所など |
||||||||||||
| 不動産の相続登記! | ||||||||||||
| 不動産の相続登記は、後日に相続により取得した不動産を処分する際などに必要になります。 不動産を任意に分割して相続登記する場合には、遺産分割協議書が必要になりますが、相続 人がお一人の場合は、当然不要になります。早めの相続登記をおすすめいたします。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 不動産所有権移転登記申請書 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 固定資産評価額証明書 相続関係説明図 遺産分割協議書等 |
||||||||||||
| 株式等の名義変更! | ||||||||||||
| 上場株式を名義変更をする場合には、信託銀行または証券代行会社に、株券本件と所定の用 紙、添付書類を添えて名義変更手続きを行います。手続きには書類の郵送等、手間がかかり ますがあわてず余裕を持って対処することをおすすめいたします。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 遺産分割協議書ないし遺言書 株券(株券が発行されていない場合は不要です。) 株式名義書換請求書 被相続人の戸籍謄本・改正原戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書 |
||||||||||||
| |
生命保険の保険金請求! | |||||||||||
| 被保険者が死亡したことを保険会社に連絡し、必要書類を提出します(提出書類は保険会社 によって異なります)。請求手続きには時効がありますので請求漏れのないようご注意を。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 各保険会社所定の死亡保険金請求書 保険証券 死亡診断書 被相続人の戸籍謄本等 保険金受取人の戸籍謄本・印鑑証明書 契約印 不慮の事故による死亡の場合は、災害事故証明書や交通事故証明書 |
||||||||||||
| |
ローン返済・抵当権の抹消手続き! | |||||||||||
| 相続人が被相続人の住宅を相続した場合、その住宅に住宅ローンがあれば、相続人はその 住宅ローンも承継するのが一般的です。住宅ローンを承継する場合、承継者の資力や返済 見込み等が考慮され、現実的に債務の返済が難しい場合には、限定承認や相続の放棄をし たり、資産売却などしてローンを返済する必要があります。ローンの返済が終われば抵当 権の抹消登記を行います。被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合には、死亡時 にその保険金が住宅ローンの残高に充当されるため、住宅ローンの承継手続きは不要とな ります。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 債務者変更申込書 被相続人の除籍謄本 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書 遺産分割協議書 |
||||||||||||
| |
年金受給権者死亡届を提出する! | |||||||||||
| 年金を受給している人や、年金受給待機中の人が亡くなった場合は、市区町村または社会 保険事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出します。 届出がない場合には、年金が死亡後も振込まれます。 振込まれた年金は後日、返還の手続きが必要になりますので、早めの提出をおすすめいた します。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 受給権者の年金証書 除籍謄本等、受給権者が死亡したことを明らかにできる書類 |
||||||||||||
| |
未支給年金請求書を提出する | |||||||||||
| 年金は受給権者が死亡した月まで支給されます。例えば、6月1日に死亡しても6月30日 に死亡しても、6月分までの年金が支給されます。 平成22年では、4月と5月分の年金支給日は平成22年6月15日(火)ですので、6月中 に亡くなられた場合は、当然6月分を請求できます。 請求できる遺族の範囲は、死亡した方と死亡当時、同一生計であった配偶者、子、父母、孫、 祖父母、兄弟姉妹です。請求順位も同じになります。 「同一生計」がポイントになりますので注意してください。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 印鑑(認印) 請求者の未支給年金を受け入れる金融機関の口座の預貯金通帳 年金証書 受給権者の死亡の事実を明らかにできる戸籍謄本もしくは抄本、死亡診断書等 死亡者と請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本もしくは抄本 住民票の写し(請求者と死亡者のそれぞれが記載されているもの) 死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書 |
||||||||||||
| |
遺族基礎年金の請求手続き(国民年金)! | |||||||||||
| 国民年金の被保険者、被保険者であった者で国内在住の60〜65歳の人または老齢基礎年金 の資格期間を満たした者が亡くなった場合に、18歳未満の子をもつ妻や18歳未満の子等に 遺族基礎年金が支給されます。 市区町村で手続きを行います。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 亡くなられた方の年金手帳 みとめ印 請求する方名義の銀行等の通帳(年金の振込み先となります。) 亡くなられた方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本 亡くなられた方の世帯の死亡記載のある住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもの) 請求する方の世帯の住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもの) ※亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です。 請求する方の住民税課税(非課税)証明書 死亡記載事項証明、または死亡診断書の写し 在学証明書ほか |
||||||||||||
| 遺族厚生年金の請求手続き(厚生年金)! | ||||||||||||
|
厚生年金の被保険者または老齢厚生年金の資格期間を満たした者が亡くなった場合に、一定 |
||||||||||||
| 【必要資料】 亡くなられた方の年金手帳または被保険者証 みとめ印 請求する方名義の銀行等の通帳(年金の振込み先となります。) 亡くなられた方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本 亡くなられた方の世帯の死亡記載のある住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもの) 請求する方の世帯の住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもの) ※亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です。 請求する方の住民税課税(非課税)証明書 死亡記載事項証明、または死亡診断書の写し 在学証明書ほか |
||||||||||||
| |
葬祭費の請求! | |||||||||||
| 国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬祭費が支給されます。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 国民健康保険葬祭費支給申請書 国民健康保険証 死亡診断書 葬儀費用の領収書 領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。 印鑑、口座振替依頼書ほか |
||||||||||||
| 埋葬料の請求! | ||||||||||||
| 健康保険の被保険者が亡くなった場合には、埋葬料または埋葬費が支給されます。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 健康保険被保険者埋葬料請求書 健康保険証 死亡診断書 葬儀費用の領収書 領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。 印鑑、口座振替依頼書ほか |
||||||||||||
| |
公共料金・電話料金の名義変更! | |||||||||||
| 公共料金の変更は電話で行えます。各種料金の支払いが自動引落しの場合は引落し口座の 変更が必要です。 NTTの電話加入権を相続する場合には、下記の書類の提出が必要になります。 |
||||||||||||
| 【必要資料】 加入等承継・改称届出書ないし電話加入権等譲渡承認請求書 被相続人の除籍謄本 相続人の戸籍謄本 |
||||||||||||
| |
自動車の名義変更! | |||||||||||
|
自動車の名義を変更する場合には、陸運局(陸運支局・検査登録事務所)で移転登録申請 |
||||||||||||
| 【必要資料】 移転登録申請書 自動車検査書 被相続人の除籍謄本 相続人の戸籍謄本 相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書または遺言書 手数料納付書 使用者の車庫証明書 |
||||||||||||
| |
事業をつぐ! | |||||||||||
| 被相続人の事業を相続人がついだ場合、事業をついだ相続人はその時点であらためて事業 を開始したことになりますので、税務署や市区町村へ各種書類の提出が必要になります (相続人が個人で既に事業を営んでいる場合には開業届等いくつかの届出は不要になりま す)。 アパートや貸家を相続した場合にも届出が必要になります。 |
||||||||||||
| 【提出書類】 個人事業の開業届出書 青色申告承認申請書 減価償却方法の届出書 状況に応じ、消費税に関連する届出書 |
※青色申告承認申請書につきましては特に 提出期限に関し注意が必要になります。
|
|||||||||||