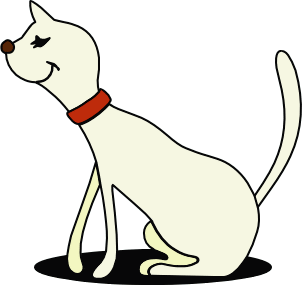| |
|||
| 相続した財産を相続税の申告期限までに国、地方公共団体、公益法人等に寄附をした場合、 一定の要件を満たすことによって、寄附をした財産については相続税がかからなくなる、 つまり、非課税となる規定があります。この場合、寄附をする財産が現金であればわりと マニュアルどおりに運べますが、土地などの不動産になれば手続きも増えてきます。 私の事案は現金の寄附でしたが、現金のケースでも金額によってはかなり注意が必要です。 間違って対象外の相手に寄附をしてしまえば相続税が課税されてしまいます。 ちなみに、寄附の金額はウン千万円でした。初めての経験でしたのでかなり気を遣いまし たが、成功のポイントは寄附の相手先団体の責任者にはるばる当事務所まで来ていただき、 寄附の受け方から送金方法等にいたるまでの一連の流れを説明してもらったことです。 金額が金額でしたので、当方も強気でわざわざ来ていただきましたが、相手方も年に何回 か寄附をいただけるケースがあるということで、丁寧に説明してもらえました。ただし、 今回の金額は【特別】ともおっしゃっていました。 なかなか私のような凡人には大金を寄附するという思いは湧いてきませんが、寄附をされ た相続人は大変喜んでおられたのが印象的でした。 |
|||
| |
|||
| 上記の事案と似た例になりますが、寄附をする相手先によっては、相続発生後に相続人が 寄附をするという順で手続きを進めると、相続税が発生するケース、つまり、非課税とな らないケースがあります。 最もわかりやすい例といたしまして、寄附をする相手先が『宗教を目的とする事業』を行 う団体に対する寄附になります。この場合は、相続が発生した後、相続人が寄附を願い出 るのではなく、被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書を作成し、その中で『もしも の場合には○○○に現金○○円と○○の土地を遺贈する。』というような記載等が無けれ ば非課税扱いされません。 ※国や地方公共団体、他の公益法人等に対する寄附の場合にも同様に、遺言は必要になり ますが、こちらは相続後でも対応可能なケースがあります。 被相続人自身の願いで財産を寄附する場合と、被相続人の意思を引き継いで相続人が相続 した財産を寄附するケースでは、少し取扱いが違ってきますので注意が必要です。 実際に遺言書を作成となれば、弁護士や司法書士も交えて相談しながらとなりますが、自 身の『財産を寄附したい。』を思われている方は意外と多いような気がします。遺言書作 成までにはいたりませんでしたが、一度、ご相談を受けたことがあります。 |
|||
| |
|||
| 相続と相続の期間が短い場合、つまり、父親が亡くなったのち5年後に母親が亡くなると いうことも起こり得ますが、このような場合には、先に父親の財産相続時に納付した相続 税、仮に1千万円としますが、このうち単純計算で1千万円×5年/10年=5百万円を 上限に、次の母親の財産相続時に発生した相続税から控除することができます。 ※実際の計算はもう少し複雑になります。 ポイントは10年以内に2回以上相続が発生した場合にこの控除が適用できる可能性があ ります。相続く(あいつづく)相続の控除です。 私の事案は2回目の相続発生時に依頼を受けました。資料を拝見すると相次相続控除の適 用がありそうでしたので、「前の相続のときの申告書の控えを見せて下さい。」と相続人 にお願いすると。「どこにおいたか忘れてしまった。」とのこと。先の相続の申告をされ た税理士は別の方でした。しかし、先の申告書がないと計算ができませんので、手間がか かりましたが、先の税理士から申告書の控えを頂きました。結局250万円ほど控除でき ました。 後々何が起きるかわかりませんので、申告書の控えは大切に保存しておくことをお勧めい たします。 |
|||
| |
|||
| 相続税が発生するような方は、現金預金を多く持っておられるというより、やはり土地を 多く所有されているという方がほとんどかと思います。今までの案件もほとんどがそうで した。そして、この土地の評価がなかなか骨の折れる作業になります。簡単に評価できる ものからかなり時間をかけて評価するものまでさまざまですが、今まで評価した中で難し かったものを少しご紹介します。 □住宅地図と実際の土地の所在地が違うものがありました。調べると結構あるようです。 相続人に確認して実際の場所が分かりました。 □土地を評価する際は、法務局に出向いて公図という資料を取り寄せます。公図(こうず) とは、土地の境界や建物の位置を確定するための地図になりますので、公図を見れば土 地の大きさや形が分かるようになっています。 登記簿謄本や名寄帳をもとに公図を取り寄せるのですが、公図を見ても土地の位置がわ からないものがありました。結局、こちらも相続人に確認すると2枚の公図を重ね合わ せて蛍光灯の光ですかすと調べていた土地が浮かび上がってきました。なぜか感動しま した。こういうケースもあるのだと素直に受け止めました。 □防火水槽になっていた土地も評価が大変でした。一度計算した土地の評価額から防火水 槽を埋めて更地にするとした場合の造成費を控除して評価しました。 その他、道路に接していない土地、路線価が付されていない土地、赤道がとおっている土 地、水路など、土地の評価はまさに千差万別ですが、ひとつずつ処理するごとに知識が身 についてくる気がしています。上記の例は、すべて同じ依頼者の所有されていた土地でし たが、たいへん勉強になりました。そして、相続人からの聞き取り作業の重要性も改めて 実感しました。 |
|||
| |
|||
| 上記事案で苦労した成果が出たのだと思いますが、次に受けた事案は生涯、思い出に残る ことになるでしょう。 広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、 都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認 められる土地をいいます。 つまりは、大きな土地ですが、この広大地に該当すれば、土地の評価を行うに際し、最大 0.35の補正率、すなわち65%引きとなるのです。 しかし、評価対象地がこの広大地に該当するかどうかを判断する必要がありますが、この 判断が非常に難しい場合があります。この事案も申告期限ひと月前までは広大地に該当し ないものと考えていましたが、最後の最後で広大地に該当すると確信し評価しました。評 価の分かれ目は『道』でしたが、評価額で4割強、相続税額で・・・(言えません)変動 がありました。 この事案でも、相続人との会話の中でヒントを見つけることができました。聞き取りの重 要性です。そして、土地家屋調査士と組んで仕事を運んでいくことの重要性も実感いたし ました。 |
|||